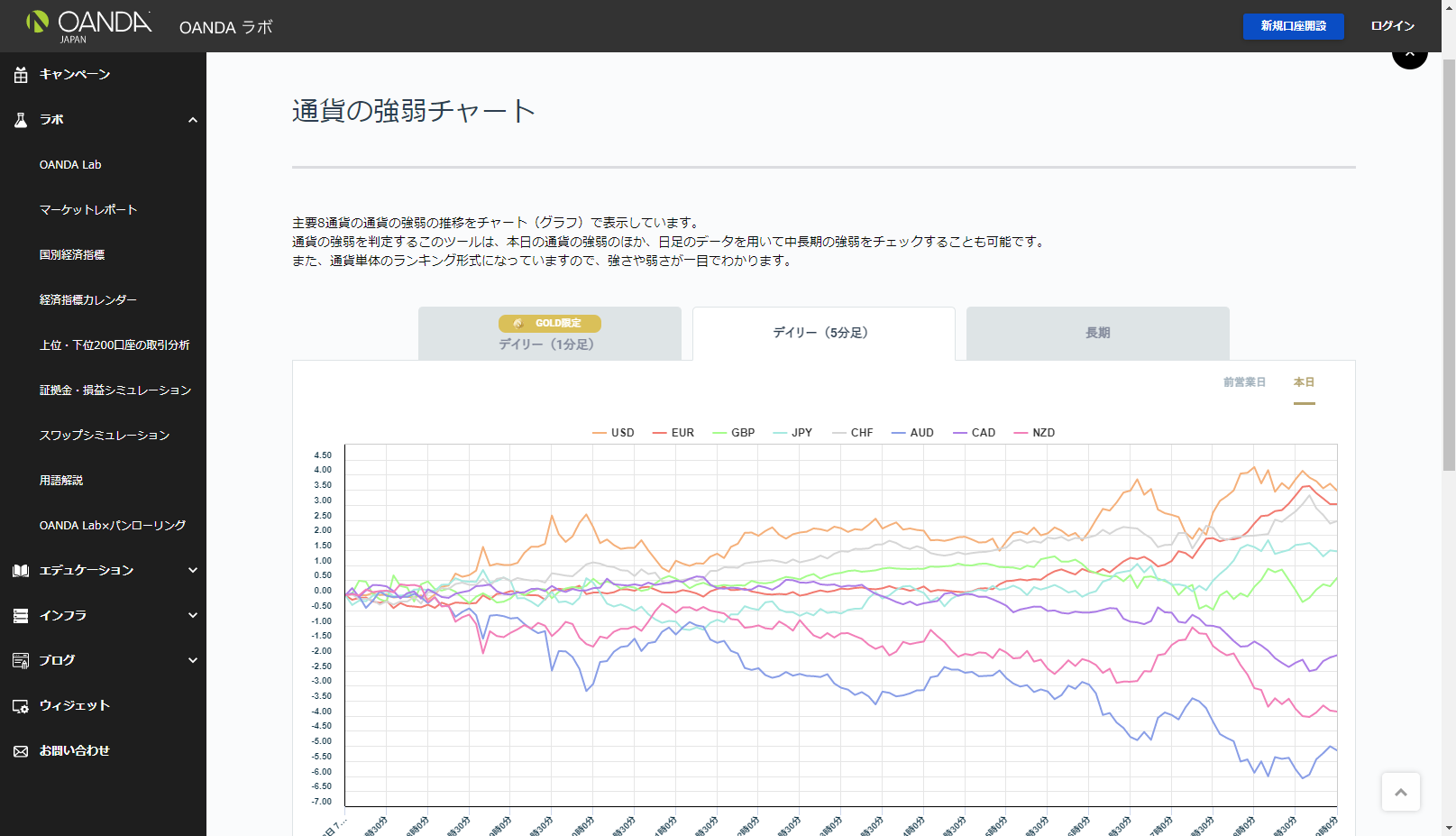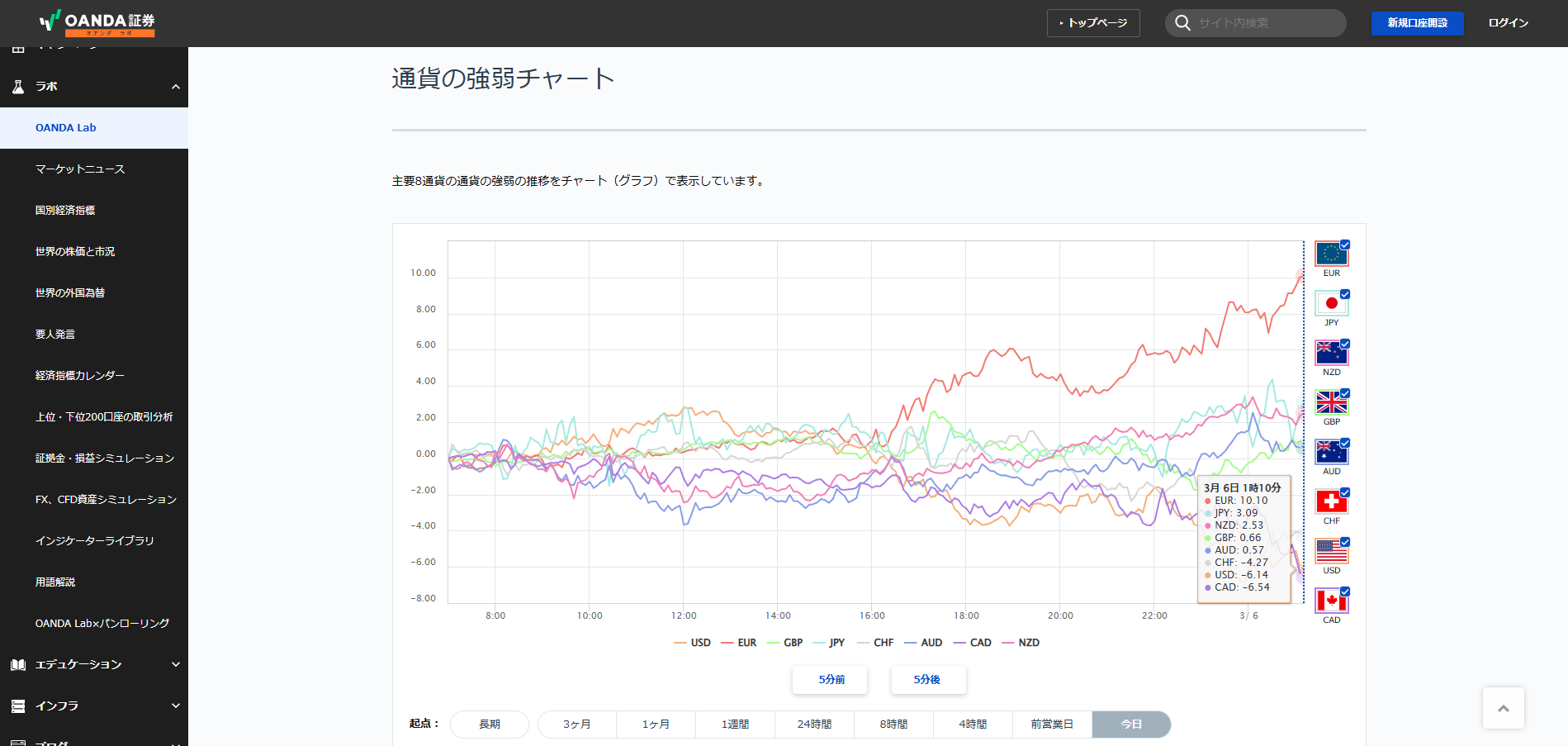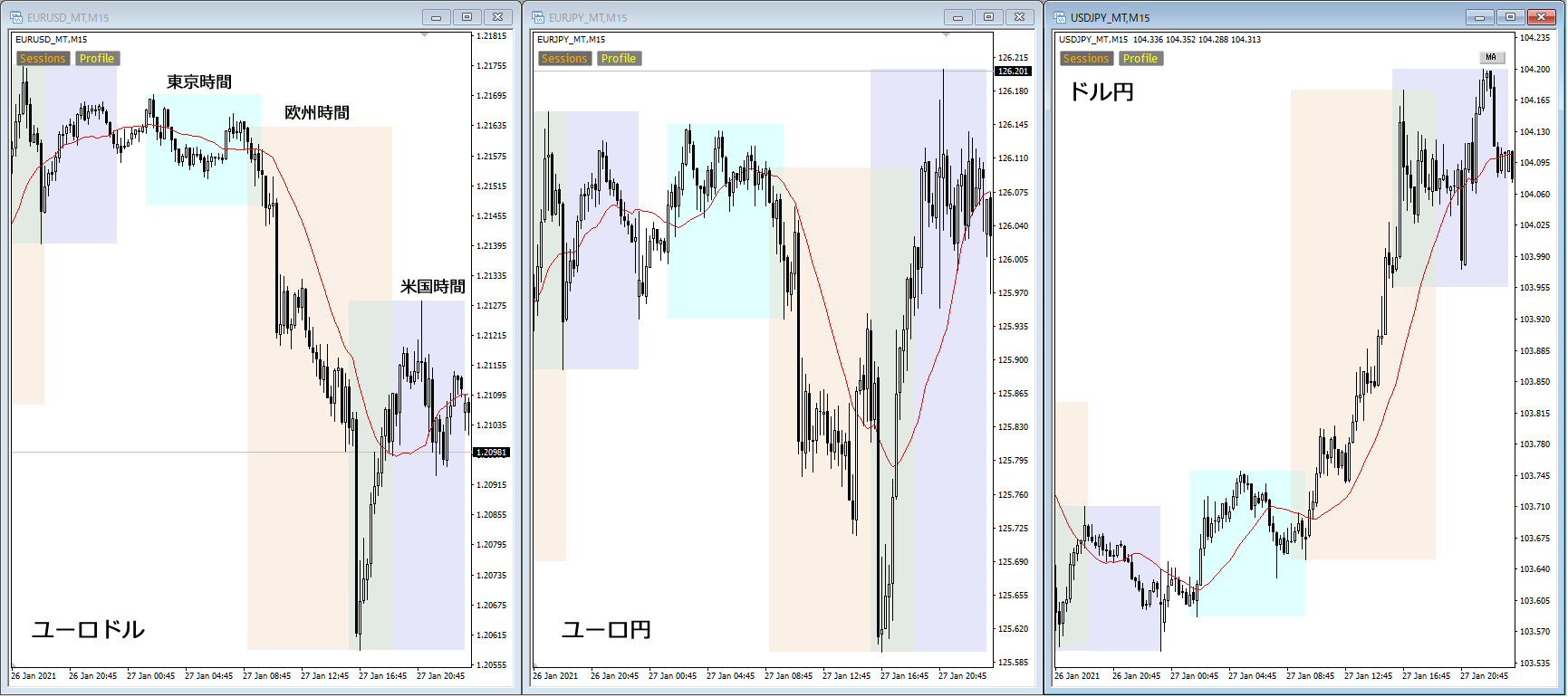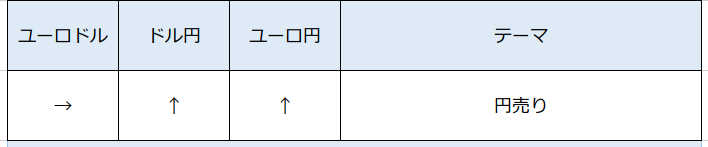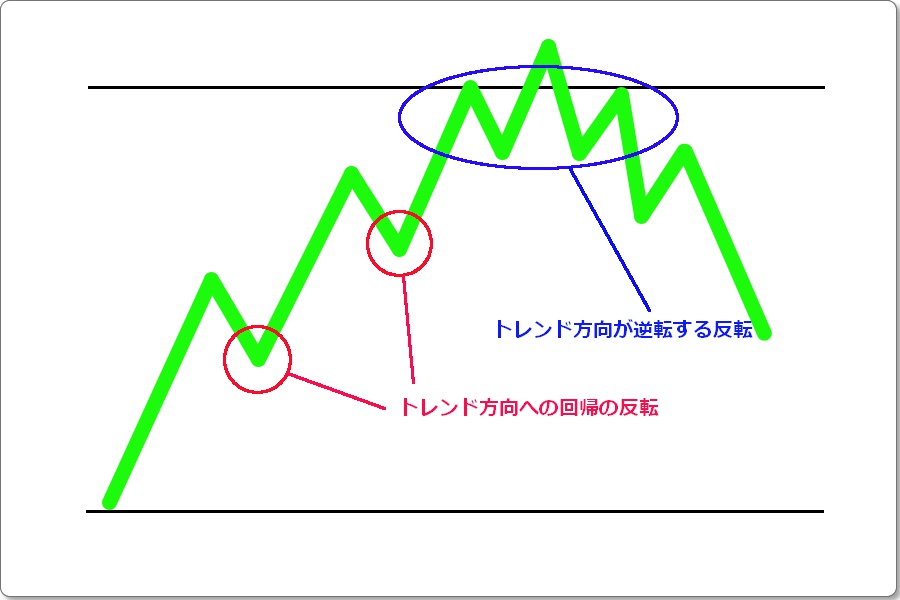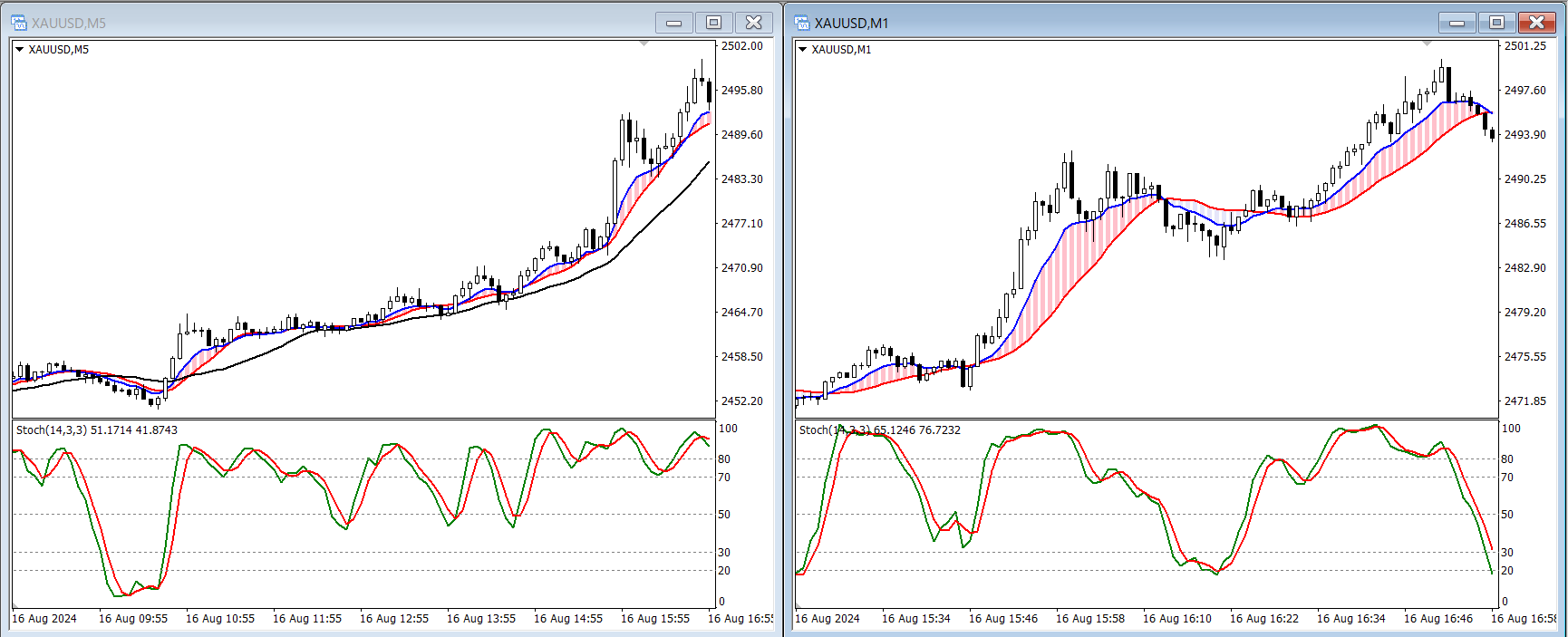さて、今回は「多通貨ペア監視のノウハウ(1)」の続編です。
前回は、多通貨ペアを監視するメリットと通貨の相関性の基本的な見方を説明しました。
ただ、相関性の把握やトレード・チャンスを求めだしたところで、キリがないということもお話しました。
なので、自分にとって適切な情報量、つまり適切な通貨ペアの数に絞っていくところから始める必要がるんでしたね。
ということで今回は、適切な通貨ペアの数に取捨選択できるようになるために、通貨に対する基礎知識のお話に入っていきます。
それじゃあ、始まり始まり~!
通貨ペア選択以前の基礎知識
では、通貨に関する基礎知識をお話をしていこうかと思います。
まぁ、FXの入門書なんかに書いてあるレベルの基礎知識ですから、知ってる人も多いと思いますが、
「そんなの知ってる~」
とか言って通り過ぎようとするのは、勝てない人あるあるです。
そんな状況から抜け出す意味でも、知っていようがいまいが、基礎固めのつもりで読んでいきましょう。
主要通貨を知ろう
世界各国、多種多様な通貨が存在していますが、FXで実際にトレードできる通貨はある程度限られています。
その中でも、実際に外為市場で取引が活発に行われている、つまり取引量の多い通貨というのは、それほど多くはありません。
BIS(国際決済銀行)による外為市場における2022年度の取引量ランキングは、
- 米ドル(6,641)
- ユーロ(2,293)
- 円(1,253)
- ポンド(969)
- オンショア人民元(526)
- 豪ドル(479)
- 加ドル(466)
- スイス・フラン(390)
(括弧内は取引量で単位は10億ドル)
となっています。
この中で特に取引の多い米ドル・ユーロ・円の3つを、「三大通貨」と呼びます。市場においてこの三大通貨が絡む取引は、全体の6割とも7割とも言われています(データの扱いによって違う)。つまり、そのほとんどが三大通貨で占められてるわけですね。
ただし、市場における取引高の割合は、
- ドルが44.2%
- ユーロが15.3%
- 円が8.3%
です。ドルが市場全体の半分近くを占めて圧倒的であるのに対し、世界3位の円は10%にも満たないわけです。4位がポンドで6.4%で、それ以下は4%にも届かないのが現実です。
三大通貨とは言え、その格差は大きいことを覚えておいてください。
で、上記8通貨のうちオンショア人民元を除いた7通貨を「メジャー通貨」と呼ぶのが一般的です。オンショア人民元は現在取引量が多いですが、2019年度の調べではスイス・フランよりも少なく、また中国人民元が自由市場での取引という観点からは特殊なため、除外されています。
また、外為市場で取引可能であっても、このメジャー通貨以外の通貨(例えば香港ドル・シンガポールドル・トルコリラなど)は、マイナー通貨と呼ばれます。メジャー通貨ですら取引量5位以下は4%に満たないわけですから、マイナー通貨は外為市場の大海原の中では、ほんのわずかな流通量であることを、頭の中に入れておいてください。
主要通貨ペアを知ろう
では、主要となる取引量の多い通貨ペアはどれなのでしょう?
2022年度の取引量のランキングはBIS(国際決済銀行)によると、
- EUR/USD(ユーロ・米ドル)
- USD/JPY(ドル・円)
- GBP/USD(ポンド・米ドル)
- USD/CNY(米ドル・オンショア人民元)
- USD/CAD(米ドル・加ドル)
- AUD/USD(豪ドル・米ドル)
- USD/CHF(米ドル・スイスフラン)
となります。
見ての通り、基軸通貨であり圧倒的な取引量を誇る米ドルとメジャー通貨の組み合わせが、取引量の多い通貨ペアですね。中でも、上位3位の合計取引量は、市場全体の半分近くを占めています。
ただし、ここで「あれ?」と思った方も多いと思います。
ランキング1位は、世界1位と2位の取引量を持つユーロ/ドル。ランキング2位は取引量世界1位と3位の取引量を持つドル/円ですが、ランキング3位は、世界2位と3位の取引量を持つユーロ/円ではなく、ポンド/ドルなんですよ。
その理由は簡単です。先ほどお話した通り、為替市場におけるドルの影響力は圧倒的だということです。なので、ドルが絡まない通貨ペアの取引量は、例えそれが取引量世界2位と3位の通貨ペアとはいえ及ばないということです。
そのため、取引高世界1位のドルと4位のポンドが繰り上がり通貨ペアでは3位となり、以下の通貨ペア順位もそれに準じる結果となっています。
このことは、通貨ペアを選択するうえで重要なポイントとなりますから、忘れずに覚えておいてください。
で、上記7つの通貨ペアからUSD/CNYを除いた6通貨ペアが、外為市場で取引量の多い通貨ペアだということを覚えておいてください。
ドルストレートとクロス通貨
で、そんな米国の通貨であるドルは、世界の基軸通貨となっていて、基本的に世界の貿易は、ドルを介して取引が行われてます。
どういう事かというと・・・
米国に対して日本や英国やらの世界各国が貿易を行う場合、取引する通貨は、米ドルと自国通貨(米国と日本なら、ドルと円)となるのは、当然なんで分かりますよね。
しかし、日本と英国が貿易する場合は、円とポンドを直接取引するわけではなく、仕組みとしては、円を一旦ドルに換えて、そのドルとポンドで取引をするんですね。
ドル以外の通貨同士では、直接取引できないんですよ。直接取引できるのは、ドルを相手にした時だけです。
なので、ユーロ/ドルやらドル円など、対ドルの通貨ペアは直接互いの通貨のやり取りが可能なので、「ドルストレート」と呼ばれます。
そして、ドルが絡まない通貨ペア(ポンド/円やユーロ/ポンドなど)は一旦ドルを挟んで取引するため、「クロス通貨」と呼ばれます。
対円の通貨ペア(ユーロ円や豪ドル円など)のことは、「クロス円」と呼ばれます。
この言葉、FX関連の話の中では常にサラッと使われますので、知らない人は覚えておいてください。
リスク・オンとリスク・オフ
金融ニュースなどで度々目にする言葉に、「リスク・オン」と「リスク・オフ」というのがあります。
リスク・オンとは、景気の見通しが明るい時に、投資家・投機家が高いリスクをとりに行く状態のことです。要するに、景気が良いからリスクの高い金融商品に手を出していくことを意味します。
それに対しリスク・オフとは、景気の見通しが悪いため、投資家・投機家がリスクの低い金融商品に手を出していくことを意味します。リスクの高い株式・原油を売って、リスクの低い債券や金を買ったりするんですね。
リスク・オフの際に通貨の場合は、リスクの高い新興国の通貨を売ってリスクの低い先進国の通貨を買います。
で、その中でもリスクが低いと考えられている通貨を「安全通貨」と呼び、その代表格が円とスイス・フランになります。
一昔前は「有事のドル買い」と言ってドルは安全通貨の代表でもあったわけですが、今ではその面影はかなり薄くなっています。近年では、有事の際は円が買われることが多くなってきました。
しかし、そんな円もここ数年、その経済における相対的地位の低下化から、安全通貨としての側面はやや薄れつつある様に感じます。(個人的な感想です)
資源国通貨
G7の様な経済主要国の主要な貿易産業は、工業製品やITサービスになりますが、それとは違って石油や鉄鉱石や石炭などの資源を主力の輸出産業とする国の通貨を「資源国通貨」と呼びます。
資源といえば石油、石油といえばアラブ諸国を思い浮かべる人も多いと思いますが、石油取引は一般的にドル建てで行われます。
そのため、外為市場における資源国通貨と言えば、主要なのはオーストラリアの豪ドルやカナダの加ドルになります。
ただし、カナダは地政学上、アメリカの隣にあることもあり、豪ドルに比べて加ドルは資源国通貨としての特徴は薄くなり、ややアメリカ寄りの値動きになりやすい特徴があります。(ただし、旬な話題としては、アメリカはカナダに関税をかける云々の話題になっていますから、値動き的にはまた違った変化が生じやすい環境にあります)
なお、ここ最近では資源通貨国として取引量は決して多くはありませんが、オーストラリアと同様に資源国であり、地理的にも近いニュージーランドをメジャー通貨7か国にプラスして、通貨の相関関係を捉えようとする傾向がある様に思います。(これも個人的見解に過ぎませんが)
各通貨の特徴
それでは、以上の開設を踏まえたうえで、代表的な通貨の特徴をサラッとお話していこうと思います。
米ドル
既にお話した通り、外為市場の中でも米ドルは圧倒的な取引量を誇る基軸通貨ですから、値動きは安定的です。(この場合の安定的とは、値動きが緩やかという意味ではなく、価格が飛んだりノイズが生じにくいという意味です)
さらには、政治経済における超大国であるアメリカのニュースは、他の諸外国に比べ収集しやすい環境にあります。
そのため、最も取引しやすい通貨であると言えます。
ユーロ
外為市場で2番目に取引量の多い通貨のため、ドル以外の他通貨と比べると安定的な値動きとは言えるでしょう。
しかし、ユーロはEU各国の共通通貨のため、「欧州」という括りだけではなく、EU内の1国の特別なニュースに反応する可能性も高くなります。例えば、フランスやオランダなどのEUの大半の国の経済状況が好調でも、ドイツ1国の経済状況が悪化することで、EUそのものの値動きは影響を受けます。
その様に、ファンダメンタルズ的な判断は、単独な通貨に比べると単純ではないとは言えるでしょう。
しかし、テクニカルで判断する場合は、世界第2位の取引量であるユーロが、取引しやすい通貨の1つであることは間違いありません。
ポンド
金融大国の英国の通貨であるポンドは、投機性が高くなりやすい特徴から、ボラティリティ(値動きの幅)の高い通貨の代表格です。そのため、トレーダーにとって人気の高い通貨であることは間違いありません。
EUとは地理的・経済的にも結びつきが強いため、ユーロが売られればポンドも売られるなど、ユーロと似た様な傾向を示すことが多いです。
豪ドル
既に解説した通り、主な経済主要国が工業・IT産業中心であるのと違って、オーストラリアの主な輸出産業は鉄鉱石や石炭などの鉱物資源です。
そのため、豪ドルは資源国通貨と呼ばれ、経済主要国(米国・EU・英国・日本)とは違った値動きを形成します。
また、オーストラリアは米国やEUとは地理的にも遠く中国の影響も受けやすいため、加ドルに比べると豪ドルは独自の値動きを形成しやすい通貨です。
地理的に近く同様に資源国であるニュージーランドの通貨は、豪ドルと似た様な値動きになりやすい傾向にあります。
スイスフラン
スイスは地理的にはEUに近いですが、永世中立国ということで、政治的結びつきがEUや米国などの経済主要国とは全く違う立ち位置にいます。
そのため、値動きもそれらの国とは違った様相を呈します。
中立国であるがゆえに、スイスフランは安全通貨としての側面があり、アメリカの政情不安等から米ドルを手放す傾向にある際、逆にスイスフランが買われるケースも多々あります。
円
日本の通貨である円は、世界3位の取引量であり、また投機的な取引よりも輸出入における実需の割合が高いため、その値動きは安定的です。
また円は安全通貨としての側面が強く、相場がリスク・オフに傾くと、円が買われやすい傾向になります。
ただ、ここ数年の印象でいえば、日本経済の相対的な低下のせいもあってか、以前のような安全通貨の一面は薄れてきている様に思えます。
日本のトレーダーからすると、日本の通貨である円の情報は手に入れやすい環境にあり、また他の通貨資産を円換算する必要もなく資金管理が比較的楽なため、人気の通貨です。
通貨ペア選択のためのポイント
通貨における基礎知識を、ここまで解説してきました。
ここからは通貨ペアを適切に選択するために、押さえておきたいポイントをお話します。
取引量とボラティリティ
ボラティリティとは、ご存じの通り価格変動の大きさのことです。ボラが大きいというのは値動きの幅が大きいということで、逆にボラが小さいというのは価格変動幅が小さいということです。
で、トレードというのは、売買差益を狙って行なう行為ですから、ボラティリティが大きければ大きいほど、取引通貨としての魅力が増します。スプレッドや手数料のことを考えたら、尚更のことです。
ただし、このボラティリティに関して言うと、実は大きく2つに分けて考えていく必要があります。それは、
- 取引量を伴うボラの大きさ
- 取引量が少ないが故のボラの大きさ
です。
取引が活発になり取引量が多くなると、ボラは大きくなります。
ご存じの通り、東京時間よりもロンドン市場の取引が大きくなりますから、ボラは大きくなりますし、ロンドン市場とニューヨーク市場が重なる時間はさらにボラが拡大します。
またトレンドが発生している場合はもちろんボラは大きくなりますが、これも発生してる方向に対して取引が活発になっているわけですから、取引量を伴ってボラが拡大しているということになります。
ですから、取引量が増大するとボラが拡大するというのは正しい判断です。
しかし、逆に取引量が少ない場合でもボラが拡大したりするんですよ。
取引量が少ないということは、市場で売買する参加者も資金量も少ないということです。
であれば、ちょっと多めの買いが入った途端に大きく価格は上に上がり、ちょっと多めに売りが入った途端に価格は大きく下がるわけですね。
これは単に注文枚数が少ない、つまり市場が閑散としているために、値が飛んでしまいやすいということです。値が飛んでしまっているため、見た目にはボラが大きくなるわけです。
であれば、上に大きく値が伸びた様に見えても、それは買い手が閑散としていたのが理由であって、値動きの方向性が固まって上に上昇したわけではないかもしれません。そうであれば、上の方でちょっと大きめの売りが入った途端に今度は逆に大きく下に値が落ちたりもするんですね。
つまり、取引量の伴わないボラの大きさというのは、方向性が当てにならないんです。ノイズが多くなりがちで、信ぴょう性に乏しいということになります。
以上のことから、取引量が活発だからボラティリティが大きくなる場合と、取引量が少ないからボラティリティが大きくなる場合の2パターンがあることを、覚えておいてください。
取引量とトレードの関係
さて、ここまで取引量に着目してお話してきましたが、何が言いたいかというと・・・
取引量が多い通貨ペアをトレードするというのは、リスクを抑えるということに繋がるということです。
取引量の少ない通貨ペアは、注文量も乏しいため、大きく動くという特徴がありますが、先ほどお話した通り、それは単に値が飛んでるだけってことが結構多いわけです。上に行ったと思っても直ぐ下に大きくぶれる可能性も大きいわけで。
要するに、取引量の少ない通貨ペアをトレードするというのは、売買の方向性に対する信ぴょう性が薄いというリスクを孕んでいるということです。
また、注文数が少ないため、取引が成立しないことが出てきます。つまり、買いたい時に買えず、売りたい時に売れないことが出てきやすいんですね。
ファンダメンタルズ的に大きな異変があった場合は、なおさらです。自分のポジションと反対に動いた場合は、ストップ注文が約定できずに、取り返しのつかない損失を被る可能性があるんですね。
わずか数十分で歴史的暴落となったスイスフラン・ショック(2015年)は記憶に新しいと思います。安全通貨と呼ばれ、取引量も世界第7位のスイスフランですら、非常時にはそうなってしまうんですよ。
マイナー通貨と呼ばれる通貨は、そういった危険性を常に孕んでいると言えます。
しかし、取引量が多い通貨ペアというのは、注文がそこら中に散らばっているため、価格推移が比較的安定する傾向にあります。
要は、ノイズが少ないってことです。一時的な目先の値動きに振り回されることが少なくなるため、取引量が少ない通貨よりも多い通貨の方が、取引しやすい傾向にあります。
まぁ、あくまで比較の問題なので、取引量が多いからノイズがないってわけじゃありませんけどね。
以上のことから、リスクを承知でマイナー過ぎる通貨を選択したいなら、それはそれで止めませんが、余計なリスクを抱えたくないのであれば、出来るだけメジャーな通貨同士のペアで取引することをお勧めします。
スプレッドについて
トレード・スタイルによるシビアな差
スプレッドとは、ご存じの通り買値と売値の差額のことで、トレーダーからすると実質な手数料の様なものになっています。
なので、トレード回数が多くなればなるほど、トレードのトータル収支に大きく影響を与えますから、トレード・スタイルによってその重要度は大きく変わります。
例えばスイング・トレードの場合なら、1ヶ月にトレードする回数は少ないですし、1回のトレードの損益幅は大きいですから、スプレッドそのものがトータル収支に占める割合は少ないですよね。
しかし、デイトレの場合になると、月のトレード回数はもっと増えますし、トレード1回の損益幅はスイングに比べ小さくなりますから、スプレッドの占める割合は大きくなっていきます。スキャルピングであれば、それはもうかなりの負担になってしまいあす。
ちょっと単純化して比較してみましょうか。スプレッド1pipsの通貨ペアをトレードしたとしましょうか。これをトレード回数で比較すると、
- 月に3回しかトレードしかしない(スイング)なら、スプレッドとして差し引かれる損失は、月間3pips
- 月に20回トレードする(デイトレ)なら、スプレッドとして差し引かれる損失は、月間20pips
- 月に200回トレードする(スキャルピング)なら、スプレッドとして差し引かれる損失は、月間200pips
1回のトレードでの利益幅が小さくなるトレード・スタイルになるほど、ロット数は増える傾向にありますから、単純にスイングがロット1、デイトレがロット2、スキャルピングがロット3として考えると、
- スイングは、月間3pips×ロット1=3pips
- デイトレは、月間20pips×ロット2=60pips
- スキャルピングは、月間200pips×ロット3=600pips
改めて考えると、結構な差ですよね。取引回数が増えれば増えるほど、また取引額が増えれば増えるほど、スプレッドとしてトレーダーが被る損失(「損失」と言い切った方が理解しやすい)は、倍々ゲームで増えていくわけです。
このこと、実はFXを始める最初のうちは、結構気にするんですよ。スレッドのできるだけ小さなFX業者を探したりなんかしてね。
ところが、トレードを重ねるうちに、なぜか気にしなくなってしまうんですよ。負けが続くと、そういった感覚がマヒしちゃうのかな?
ま、以上のことから、取引回数が少なく、また1度のトレードにおける金額が極端に大きくなければ、それほどスプレッドは気にしなくても良いですが、取引回数が多いトレードスタイルの人は、スプレッドに対してシビアに構える必要があります。
通貨による違い
通貨によってスプレッド幅には違いがあるのは、ご存じだと思います。
原則、メジャー通貨はスプレッドが狭く、マイナー通貨はスプレッドが広くなる傾向がありますが、この説明だとちょっと正確性に欠く感じかな。
もう少し正確性をもって分かりやすく説明すると、
- 取引量が圧倒的に多いドル・ストレートは、スプレッドが狭くなる傾向
- 取引量がそれに次ぐユーロや円もスプレッドが狭くなる傾向
- 国内業者のFX口座であれば、クロス円のスプレッドはより狭くなる傾向
になります。
そのため、スプレッドの観点でいえば、ドル・ストレートかクロス円を選択することが有利なトレードになります。
ちなみに、国内業者と海外業者との比較では、
- 国内業者では、最もスプレッドが狭いのがドル円、次いでユーロドル。クロス円の方がスプレッドが狭い傾向にある
- 海外業者では、最もスプレッドが狭いのがユーロドル、次いでドル円。ドル・ストレートの方がスプレッドが狭い傾向にある
といった感じになるでしょうか。
スワップポイントについて
これもまぁ、ご存じの方ばかりだとは思いますが、スワップポイントとは簡単に言ってしまうと、その通貨を買った時につく金利の様なものです。
原則的にマイナー通貨の方がスワップポイントが高く、メジャー通貨の方が低い傾向にありますが、一概には言えません。同じメジャー通貨、同じマイナー通貨でもポイントには差があります。
これは、各国の金利政策によって違いがあるためで、基本的に通貨金利の高い国の通貨のスワップはポイントが高くなりますし、金利の低い国の通貨はポイントが低くなります。
また、これは実際にトレードした際にうっかりし忘れやすいことなんですが、スワップポイントは買った場合にはプラスで付きますが、売った場合はポイントが引かれます。
なので、スワップで差益を考える場合は、必ず「スワップポイントが高い通貨を買い、スワップポイントが低い通貨を売る」という組み合わせの通貨ペアを選択する必要があります。
ただ、スワップポイントというのは、1日ごとに加算されますので、日計り(その日に買ってその日のうちに決済する)の場合、スワップポイントはつきません。
なので、デイトレやスキャルでは全く気にする必要がありません。スワップポイントを気にするのは、ポジションを次の日以降まで持ち越すトレーダーのみです。
とはいえ、スワップポイントは、取引額や狙う差益から比べるとそれほど大きくはありません。スイング・トレードをする際に、スワップを気にしすぎると、むしろチャンスを逃すこともありますから、気にかけ過ぎは禁物かもしれません。
ちなみにですが、スワップポイントそのものを狙う投資スタイルはあります。長期積み立てによって金利で利益をもらう発想と同じなんですが、これには注意が必要です。
スワップ目当てで長期保有してても、為替差損(つまり価格が買値よりも下がっていく)が膨らんでしまえば、結果として大きな損失を被ることになるというリスクがあるからです。
今から20年ほど前、この投資方法で世界を席巻した日本の主婦達が沢山いて、「ミセス・ワタナベ」と呼ばれるほど海外でも知られる存在でしたが、リーマン・ショックと共に彼女たちは財産を失いました。
なので、正直この投資スタイルはお勧めしません。もしやるのであれば、レバレッジをかけない「外貨預金」のスタイルの方が現実的です。為替差損のリスクは消えませんが、レバレッジをかけていない分、損失はまだ限定的です。
またミセス・ワタナベがやっていた様なスワップ・ポイント目当ての投資スタイルは、多大なレバレッジをかけることでスワップ収益を大きくし、その収益だけで日々の生活を潤そうとするものです。つまり、長期投資なのに長期的な視野に立っていないわけで。
しかし、外貨預金のスタイルは、考え方としては長期積立預金に近く、「将来的に資産が数パーセント増えたら良いな」という趣旨のものです。
だからと言って、個人的にお勧めするわけではありませんが、ちょっとスワップの話が出たんで、比較対象として採り上げてみました。
なお、このブログは取引差益を狙う「トレード」の話が主旨なので、スワップ・ポイント狙いについては、ほぼ重要視していませんので、あしからず。
総括
さて、通貨選択の基本的なポイントについて、いくつかお話しました。
ここまでお話したことを、簡単にまとめると、
- 取引量の多い通貨・通貨ペアを選択することで値動きや売買の不安定さというリスクを回避することができる
- ボラティリティの高い通貨ペアを選択することは大切だが、取引量の伴わないボラティリティはリスクが大きい
- スプレッドは取引回数や取引額が多くなればなるほど比重が大きくなり、気にする必要が出てくる
- スプレッドを考慮するなら、ドルストレートかクロス円が有利
- スワップ・ポイントは、日計りなら気にする必要はなく、スイングでも損益に対する比重が少ないのであれば、あまり気にしない方が良い
ということになります。
で、これらを考慮するならば、通貨選択の基準はもうハッキリしてますね。
- 選択する通貨は、取引量・ボラティリティ・リスクを考慮すると、メジャー通貨のみ
- 選択する通貨ペアは、スプレッドの負担を考慮すると、ドル・ストレートとクロス円に絞る
ということです。
通貨ペア選択する際には、ドル・ストレートやクロス円であり、そしてドルや円に対する通貨は、全てメジャー通貨で構成するべきなんですよ。
いくらドルや円の取引量が大きいからと言って、売買先がマイナー通貨であれば、取引量は必然的に少なくなりますから、その分リスクも背負いやすくなるわけです。
さて、この選択によって監視する通貨ペアは、21種類から11種類へと、一気に減らすことができました。
しかし、それでも・・・
監視する通貨ペアは、一気に半分になりました。
が、実際はその数でも、ちょっと微妙です。
11通貨ペアをチャートを並べてみるとこんな感じになります。
パッと見で「ムリ!」って思う人もいるでしょし、「大丈夫だろ」って思う人もいるかもしれない、微妙なラインです。
でも、実際やってみれば分かると思いますが、
「どの通貨ペアがどの場所にあって、どれとどれを見比べたら相関関係が分かって・・・」
ってな感じで、11個もチャートが並んでいると、結構ゴチャゴチャしちゃいます。
しかもそんなゴチャゴチャした情報を、時間をかけずに正確に把握し判断するってなると、実はこの数だってかなり大変なんですよ。
この数の監視を使いこなせる様になる時間と労力があるんであれば、個別の通貨ペアの分析力アップのための検証と練習に費やした方が、現実的じゃないですかね?
そう、努力の方向性は間違っちゃダメなんですよ。
僕は年齢と共にミスが増えるようになったため、次第に監視する通貨ペアの数は減らしてきました。今の僕の監視通貨ペアは、8種類です。
で、相関性の見極めとトレードする通貨ペア選択をする上では、この8つの通貨ペアという数が適切なのかな、と個人的には思ってます。
なので、これから多通貨ペア監視に取り組もうという人は、8つの通貨ペアで監視することから始めた方が良いと思います。
さて、基本的な知識の方は、この辺まで分かってもらえたらOKかと思います。ここから先は、実践に結び付けるための応用編をお話していこうと思います。
が、案の定お話が長くなってしまいましたので、次回に持ち越しです。
次回からは、
- 監視通貨ペアを8つに絞ること
- 僕が実際にやっている多通貨監視の実践的なやり方の解説
- 実際にトレードするための通貨ペアの選択手順
をお話していこうと思います。
ある意味、今までは基本的な話ばかりで退屈だったかもしれませんが、次回からは一気に実践的な方法論に入っていきますので、お楽しみに。
それじゃあ、また。